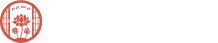ようこそ、なもぶろぐにお越しくださいました。
案内人でございます。
はてさて、そろそろ2月と相成ります。京都では神社だけでなく、多くのお寺さまでも節分会が催されます。なかでも、壬生寺の節分会厄徐大法会は有名です。
もともと季節の分かれ目、立春の前日を指す『節分』。日本には宮中行事として中国から伝わりました。平安時代後期に、白河天皇が新年を迎える厄除けとして、壬生寺で、節分会厄徐大法会が執り行われたのが、全国の節分会のはじまりになったと云われています。壬生寺の節分会では、炮烙奉納、お練り供養、大護摩供養、厄除け護摩祈祷、星祭と祭事はさまざまな行事が行われます。
今年(2022年)はコロナの影響があるので取り止めになるかもしれませんが、例年なら有名な壬生狂言も行われます。節分の壬生狂言は、私の記憶が正しければ「無料!」です。産経新聞さんが、YouTubeに映像をUPされていたので、LINKしておきますね。
お寺さまにお尋ねしますと、仏教における『鬼』とは、心の中の煩悩を指すそうです。妬みや嫉み、憎しみなどの誰しもが負の思いを持っているのですが、その煩悩を追い払い、清々しい気持ちで新年を迎える、それが仏教における節分の意味なのだそうです。
豆を撒くのは、これも中国が起源で、豆は生命力が強く、疫鬼を追い払うと信じられていたうえ、「魔(の)目に豆を投げつけて魔を滅っする『魔滅』」に通じているそうです。
京都の行事に溶け込んだ節分と仏教のランデブー、ぜひお楽しみくださいね。